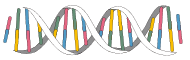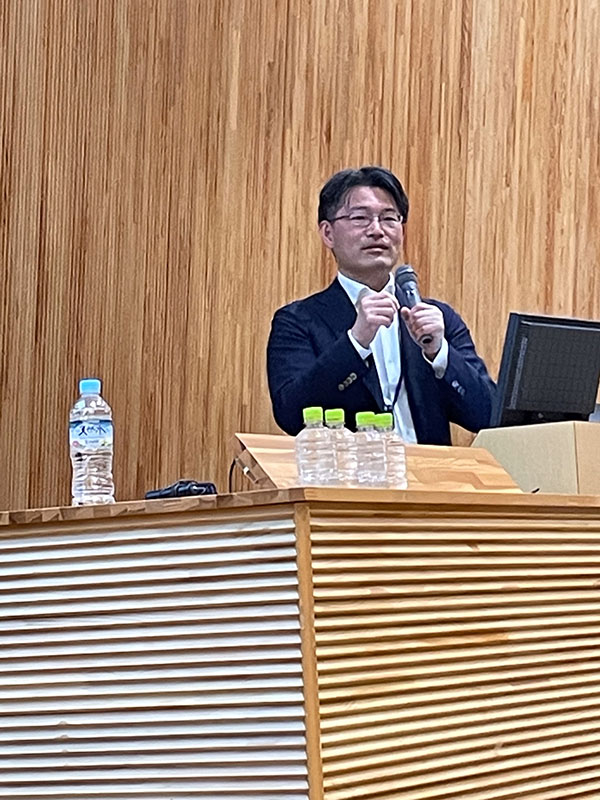2023年はヒトゲノム解読の完了宣言から20年。国際的な「DNAの日(4月25日)」の関連イベントとして2023年4月23日(日)に開催されたシンポジウムの内容を紹介するレポート。ヒトゲノム計画を“中の人”として経験した榊佳之さんの裏話満載のお話のあとも、イベントは続いた。
見えないDNAを市民参加実験で見える化
次の登壇者はNPO法人くらしとバイオプラザ21の常任理事である佐々義子さん。「レジェンドの後に話すのはとてもやりにくい」と冒頭でさっそく場を和ませた佐々さんが話してくれたのは「DNA粗抽出実験の実践から」。DNAという「よく聞くけれど見たこともないもの」を見えるようにする実験だ。子どもが体験できるDNA実験としては、教育目的の遺伝子組換え実験があるが、細胞培養器や紫外線ランプといった器具が必要な上、指針に則って実施する、実験後は組換え微生物を確実に死滅させるようにするなど、個人が手軽に楽しく行えるようなものではない。
佐々さんたちが提供している親子を対象にした「DNA粗抽出実験」では、洗剤や塩、すり鉢、計量スプーン、消毒用エタノール、スーパーで普通に売っている食材など、あえて家庭にある道具や材料を使っている。手順はシンプルで、すり鉢を使って物理的に食材中の細胞をこわし、洗剤(界面活性剤)で細胞膜や核膜を溶かす。エタノールを加えて沈殿させると、凝縮したDNAがモヤモヤとした“もの”として現れてくる※。
※このDNAはヒストンたんぱく質などがついている状態で、そのまま電気泳動にかけられるような精製された状態ではない。このことを佐々さんは何度か繰り返し説明していた。DNA「粗」抽出実験としているのもそのためだ。
使う食材を鶏肉、ブロッコリー、トマト、バナナ、ドライイーストなどと変えることで、DNAがたくさん取れたのはなぜか、あまり取れなかったのはなぜかなどの考察ができる。水分が多かった、鮮度がよくなかったなどといった考察は、身近でよく知る材料を使っているからこそ可能になるのだろう。さらに、動物、植物、微生物というまったく異なる生き物からでも、同じ手順で見える化できることから、これらのDNAが同じ物質であることに気がついてほしいと佐々さんは言う。
実践者ならではの気づき
裏話として、DNAが取りやすい食材に関するエピソードを佐々さんは紹介してくれた。日本では魚の白子やブロッコリーがよく使われてきた。生殖器官(精巣やつぼみの集まり)であるこれらの部位はDNAの含有率が高いからだ。一方、アメリカの博物館でバナナが使われ、実際によくDNAが取れる。黄色い皮をむいてしまうので、つぶしにくい繊維がとりのぞかれていて細胞が壊れやすいのが理由と考えられる。「実際にやっている人たちならではの気づき」と佐々さん。
食や環境をテーマにしたDNA関係の実験は、このDNA粗抽出実験のほかにも、遺伝子組換え食品からのタンパク質抽出実験、前述の遺伝子組換え実験などがあり、学校教育や社会教育として、子どもや教員、一般向けに(必ずしも十分ではないかもしれないが)実施されている。啓発のための資料もある。一方、医療、つまりヒトをテーマにしたDNA関係の話題となると、実験コンテンツも少なく、啓発のための資料も少ない。病気に関しては患者さんとその家族を対象にしたパンフレットなどが疾患ごとにあるが、健康な人向けの啓発資料となると少ないと佐々さんは指摘する。
ヒトをテーマに、つまり医療の切り口でDNAを知ってもらう活動がDNAの日をきっかけに広まってほしいと佐々さんは講演を締めくくった。
ゲノム診療で何ができる?
話題提供者としては最後に演壇に立ったのは、東京医科歯科大学病院 遺伝子診療科講師の江花有亮さん。「ゲノム診療の今とこれから」と題して、実際にゲノム情報がどのように医療の場で使われているか、今後、使われるようになるかを、架空の臨床例を交えながらわかりやすく紹介してくれた。
一口に病気といっても原因はさまざまだが、多くは遺伝要因と環境要因の両方がかかわっている。いわゆる難病の多くは遺伝要因が比較的大きく影響するが、感染症などは環境要因の影響が大きい。一方、がんや生活習慣病などの“よくある病気”は、遺伝と環境の両方の要因が絡んでくる。がんであれば、遺伝的な体質としてはリスクが高めの人でも、食事や運動などで健康的な生活を意識していればがんにならずにすむかもしれないし、遺伝的な体質ではリスクの低い人でもタバコを吸ったり、アスベストを吸い込んだりすれば、リスクは高くなってしまう。
ただ、こうした“よくある病気”には1つや2つではなく、たくさんの遺伝子がかかわっていることが多い。これを江花さんは砂金にたとえた。いわゆる遺伝性疾患にはたった1つの遺伝子の変異が発症に結びつくものもある。これは大判・小判のようなもので、1枚で大きな影響力がある。一方、がんやいわゆる生活習慣病、あるいは身長や才能などはたくさんの遺伝子がかかわることがわかっている。これらは砂金のようなもので、1つひとつの影響力は小さくても積み重なることで影響が大きくなる。
医療で遺伝情報はどう使われる?
江花さんは典型的な遺伝性不整脈の臨床例(架空)で、遺伝情報がどのように医療で使われているかを紹介してくれた。学校の健康診断で心電図に異常ありとされた13歳の少年Aの例だ。サッカーのプレー中に失神したこともあるので、大学病院で採血や心臓エコー、レントゲンなどの精密検査を受けたが異常なし。でも、走りながら心電図をとると異常ありとなる。実はお母さんもA君と同じように心電図で異常ありと言われたことがあるものの精密検査では異常なしと言われていた。また、このお母さんの兄弟は突然死をしていた。こうした家族歴もあってA君の遺伝学的検査をしたところ心筋の収縮にかかわる遺伝子の塩基配列に参考配列とは違いのある「病的バリアント」「VUS」が1つずつ見つかった。病的バリアントとは病気の原因となるような配列の変化、VUSは臨床的な意義がまだわからない配列の違いのこと。前者は医療介入の対象となり、A君の場合ならば激しい運動を避けるようにしたり、状況によっては小さな除細動器を埋め込むといった予防法がある。血縁者が希望するならば遺伝カウンセリングを勧めることもできるだろう。一方、VUSのほうは、まだ評価が定まらないので、医療ではなく研究の対象となる。
「みんな」の参加が必要
こうした砂金のような遺伝子の研究には、多くの人の参加が必要となる。生活習慣病と遺伝とのかかわりでいえば、例えば心房細動では、1997年に3家族43人のデータ解析から遺伝子のだいたいの存在位置がわかった。2007年には2万3699人のデータ解析からリスクになりうる3つの遺伝子多型(参考配列と違う配列)、2017年には16万4976人のデータから数十の砂金クラスの遺伝子多型がかかわっていることがわかった。今では、これらのたくさんの遺伝子を統計的に解析して、多遺伝子リスクスコアを計算で求めることも提唱されている。こうした研究によって、老化や生活習慣病の影響で起こると思われていた心房細動にも遺伝的な要因があるとわかり、それに応じて予防、診断、治療の方法も変わっているという。
大事なのは、多数の人の協力がないとこうした研究は進められないということ。そして、誰もが病気のリスクを高めるような遺伝子をほぼ必ず持っているという点だ。誰もが他人事でないし、研究への参画という形で積極的にかかわることもできる。だからこそ、みんなで考える「ゲノムとわたし、あなたとゲノム」なのだ。
どんな課題があるのか──ディスカッションパート
すべての話題提供者が登場するディスカッションパートでは、会場とオンラインの両方からたくさんの質問が寄せられた。いくつかを取り上げよう。
会場から出たのは、あるカップルが赤ちゃんを得たことに対して。NHKがこの話題を番組で取り上げたところ、赤ちゃんをもつことに批判的なコメントが来て、質問者は衝撃を受けたという。江花さんは「調べれば誰でも病的バリアントやVUSが見つかるもの。それによって個人が否定されることはあってはならない」。
オンラインからは「ゲノム解析で考えられる最大のメリット・デメリットは」という質問。榊さんは「メリットは、病気へのリスクを予測して備えることができること。デメリットは、就職などで不利な扱いを受ける可能性があること」。佐々さんは榊さんの答えに加えて「私たちは似ているけれど、みんな違うとわかること。これを優しさに結びつけることができないのならば、私たちはなぜ人間をしているのか?」と語った。
さらに、ネットなどで手軽に申し込める遺伝子検査ビジネスについても質問があった。吉田さんは「病院で遺伝子検査の結果をお伝えして理解していただくのは、かなり時間のかかるプロセス。結果だけで詳しい説明がないと不安になる人もいそうだ。社会でのDNAへの理解が高まればそういうサービスがあっても良いと思うが、今はまだその時期ではないのではないか」。江花さんも「まだ解釈がかたまっていないものもある。“わからないこと”の扱いが定まってない」という。佐々さんは、pH値はわからないが酸性かアルカリ性かはわかるリトマス紙とpH値もわかるpHメーターにたとえた。「リトマス紙(ビジネス商品としての遺伝子検査サービス)の結果で何かマズイとなったら、pHメーター(病院での検査)を利用するのもいい。リトマス紙の結果で高価なサプリを勧めたりするのはちょっと疑問」。
最後の質問は大判・小判クラスの遺伝子変異が原因となる、いわゆる希少疾患に関して。これらは患者数が少ないため、治療薬の開発も進みにくい。質問者は米国での現状を踏まえてのものだったが、吉田さんは「日本でも同じ悩み。ただ、全ゲノム解析などで診断は早くなりつつあり、これらが普通の医療になる時代はそんなに先ではない」との答え。榊さんは肝移植以外に治療法のなかった遺伝性アミロイドーシスの例をあげた。原因となる遺伝子が見つかってから治療薬ができるまでに40年弱かかった。遺伝子の変異と疾患をつなぐメカニズムを調べ、創薬につなげるのに時間がかかったからだ。榊さんは「でも、どの病気も取り組んでいる研究者は必ずいる。治療法をつくろうと一生懸命やっている人が必ずいる」と熱を込めて締めくくった。
予定していた2時間15分を超える長丁場のシンポジウムとなったが、始まってみればあっという間で、終わった後も会場を去らずに登壇者を囲む参加者の姿があった。